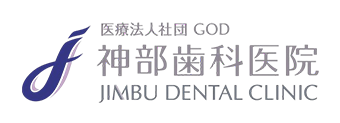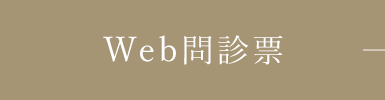- 当院のむし歯治療への考え方
- 可能な限り削らないむし歯治療
- なるべく痛みの少ないむし歯治療
- 歯の神経を残す「歯髄温存療法」の診断も可能
- むし歯の進行段階と治療方法
- むし歯になる前に歯医者へ通院しましょう!
- 唾液検査の流れ
- 関連動画
当院のむし歯治療への考え方
 歯科医院でのむし歯治療と聞いて、「痛い」「怖い」といったイメージをお持ちの患者様もいらっしゃるかもしれません。しかし、むし歯は自然に治ることはなく、進行すればするほど歯を削る量が増え、治療が複雑になります。早い段階で適切な治療を受けることで、むし歯の進行を抑え、歯を削る量を最小限に留めることが可能です。さらに、歯を失うリスクも軽減できます。当院では、患者様に定期的に通院していただくことで、むし歯の早期発見・早期治療に努めています。患者様の負担を軽減する治療方法を採用し、安心して通院いただける環境作りを心がけています。
歯科医院でのむし歯治療と聞いて、「痛い」「怖い」といったイメージをお持ちの患者様もいらっしゃるかもしれません。しかし、むし歯は自然に治ることはなく、進行すればするほど歯を削る量が増え、治療が複雑になります。早い段階で適切な治療を受けることで、むし歯の進行を抑え、歯を削る量を最小限に留めることが可能です。さらに、歯を失うリスクも軽減できます。当院では、患者様に定期的に通院していただくことで、むし歯の早期発見・早期治療に努めています。患者様の負担を軽減する治療方法を採用し、安心して通院いただける環境作りを心がけています。
むし歯予防に効果的な「唾液検査」も可能です!
むし歯の予防には、患者様それぞれのリスクを把握することが重要です。当院では「唾液検査」を用いて、お口の中の状態を科学的に分析し、個々のリスクに応じた予防対策を行っています。
唾液検査でわかること
唾液の分泌量
唾液には、汚れを洗い流したり、歯を強くしたりする作用があり、むし歯の予防に重要な役割を果たします。唾液の分泌量が少ないと、こうした作用が弱まるため、むし歯に感染しやすくなります。
唾液の質(唾液緩衝能)
唾液には、口腔内を中性に保つ「緩衝能」という働きがあります。口の中が酸性に傾くとむし歯のリスクが高まりますが、緩衝能がしっかり機能している場合は、このリスクを軽減することができます。唾液緩衝能が低い方は、むし歯にかかりやすい環境となるため、早めの対策が必要です。
口の中の細菌数
お口の中の細菌数は患者様ごとに異なり、むし歯の原因菌である「ミュータンス菌」やむし歯を進行させる「ラクトバチラス菌」の数が多いと、むし歯にかかりやすくなります。唾液検査ではこれらの細菌数を確認し、リスクに応じた予防プランを提案します。
可能な限り削らないむし歯治療

当院では、むし歯治療を行う際、患者様の歯をなるべく削らないことを目指しています。治療計画を立てる際には、患者様としっかり話し合い、以下のような点についてご相談を重ねます。
- 歯を削る必要性の有無
- 削る場合の方法と範囲
- 詰め物や被せ物の素材選び
これらのポイントを丁寧に説明し、患者様にご納得いただいた上で治療を進めます。いきなり歯を削るようなことはありませんので、ご安心ください。
治療の流れ
1カウンセリング
初回時にアンケートにお答え頂き、カウンセリングを行わせていただきます。問診・視診にて現在の患者様の状態をカウンセリングを行います。
2資料採り・精密検査・クリーニング
レントゲン撮影、口腔内写真撮影、虫歯のチェック、歯周病の精密検査を行います。その後、染め出しを行い、磨けていない部位の確認を行い、エアフローによるバイオフィルムの除去、歯石除去やブラッシング指導やご自宅でのセルフケアの重要性とご提案を行います。
3治療計画
検査結果をもとに、治療方法、期間、費用についてご説明します。
4治療開始
虫歯治療や虫歯予防治療など、患者様にあった治療をさせていただきます。
5メインテナンス
治療終了後、患者様の口腔内の状態によって、定期的なメインテナンス期間をご提案します。 定期検診の内容は、口腔内の状態の確認・染め出し・口腔内写真・エアフロー・歯石除去・ブラッシング指導やセルフケアの確認を行います。
なるべく痛みの少ないむし歯治療
 当院では、健康な歯をできる限り保存し、むし歯に感染した部分のみを精密に削る治療を行っています。そのために、「拡大鏡」や歯科専用顕微鏡「マイクロスコープ」を導入し、視野を十分に拡大した精密な治療を実現しています。これにより、患者様の負担を軽減しつつ、歯の健康を守ることが可能です。
当院では、健康な歯をできる限り保存し、むし歯に感染した部分のみを精密に削る治療を行っています。そのために、「拡大鏡」や歯科専用顕微鏡「マイクロスコープ」を導入し、視野を十分に拡大した精密な治療を実現しています。これにより、患者様の負担を軽減しつつ、歯の健康を守ることが可能です。
歯の神経を残す「歯髄温存療法」の診断も可能
むし歯が進行して歯の神経に達すると、従来は神経を取り除く治療が一般的でした。しかし、神経を取ると歯の寿命が短くなるため、当院では可能な限り神経を残す「歯髄温存療法(VPT)」を診断し、提案しています。この治療法では、感染した部分の歯髄だけを除去し、健康な神経を保存することで、歯の機能を長く保つことができます。患者様一人ひとりに最適な治療法を提案し、将来の歯の健康をサポートします。
むし歯の進行段階と治療方法
CO
歯の表面が酸により溶け始めている虫歯の前兆です。自覚症状が無く、見た目ではむし歯とは分かりにくく、歯の表面の透明感を失い白濁した状態です。
治療法
しっかりとしたホームケア、ブラッシング、フッ素塗布などを行い、再石灰化により元の健康な歯の状態を取り戻す事が可能です。
C1
COよりもむしが進行した状態で、歯が黒くなったり茶色くなったりします。エナメル質には神経が無いので、ほとんど自覚症状がありません。
治療法
患部を削って詰め物治療を行います。
C2
C1よりもむし歯が進行した状態で、象牙質に進行した状態です。冷たいものや甘いものでしみたりしてきます。
治療法
麻酔を行い、患部を削って詰め物や被せ物治療を行います。
C3
C2よりもむし歯が進行した状態で、神経にまで進行した状態です。噛んだり食べ物が穴に入ると激痛が走ったり、何もしなくても痛みを感じる事があります。
治療法
麻酔を行い、歯の神経を取り除く治療を行います。神経の治療が終わったら、土台を入れて被せ物を行います。
C4
C3よりもむし歯が進行した状態で、歯もボロボロに欠けて、神経は壊死してしまい痛みがなくなります。この状態でしばらくいると、根の先に膿の袋ができることがあります。その場合、再び激痛を感じることが多いです。
治療法
C4の段階になると、歯を残すことができない場合が多いです。根管治療などを適応できない状態の場合は抜歯を行います。抜歯を行なった場合は、ブリッジや入れ歯、インプラントなどで歯の機能を補います。
むし歯になる前に歯医者へ通院しましょう!
 当院では、むし歯や歯周病が発生してからの治療ではなく、トラブルを未然に防ぐための予防ケアを推奨しています。定期的な検査やメインテナンスを受けることでむし歯や歯周病のリスクを大幅に減らし、高齢になっても健康な歯を維持することが可能です。具体的には、正しい歯磨きの指導、クリーニング、唾液検査などを通じて、患者様の口腔環境を清潔な状態に保つお手伝いをいたします。むし歯が進行して神経に達する前に、早期治療を行うことで、多くの歯を健康な状態で残すことができます。定期的に歯科医院へ通院し、一緒に長く健康なお口を目指しましょう。
当院では、むし歯や歯周病が発生してからの治療ではなく、トラブルを未然に防ぐための予防ケアを推奨しています。定期的な検査やメインテナンスを受けることでむし歯や歯周病のリスクを大幅に減らし、高齢になっても健康な歯を維持することが可能です。具体的には、正しい歯磨きの指導、クリーニング、唾液検査などを通じて、患者様の口腔環境を清潔な状態に保つお手伝いをいたします。むし歯が進行して神経に達する前に、早期治療を行うことで、多くの歯を健康な状態で残すことができます。定期的に歯科医院へ通院し、一緒に長く健康なお口を目指しましょう。
むし歯の簡単セルフチェック
- 歯が白濁したり、茶色や黒い部分がある
- 冷たいものや温かいもの、甘いものにしみる
- 歯がかけている
- 食べ物がつまると痛い
唾液検査の流れ
1採取
 少量の水でお口全体を10秒間軽くゆすぎ、紙コップに吐き出してください。患者さんにご協力いただくのはこれだけです!
少量の水でお口全体を10秒間軽くゆすぎ、紙コップに吐き出してください。患者さんにご協力いただくのはこれだけです!
2測定
 専用の機械で、”歯の健康”・”歯ぐきの健康”・”お口の清潔度”に関する6項目を測定します。測定時間はわずか5分です!
専用の機械で、”歯の健康”・”歯ぐきの健康”・”お口の清潔度”に関する6項目を測定します。測定時間はわずか5分です!
6項目の唾液因子の意味
歯の健康に関する項目
むし歯菌
虫歯菌が多いとご存知のとおり、むし歯になりやすい事がしられています。
酸性度
唾液の酸性度が高いと、口腔環境は酸性になりエナメル質等の歯質が溶解(脱灰)しやすい事がしられています。
緩衝能
唾液には、むし歯菌や食物由来の酸を中和する機能(緩衝能)がありますが、その働きが弱いと、エナメル質などの歯質が溶解(脱灰)しやすいことが知られています。
歯ぐきの健康に関する項目
白血球
歯と歯ぐきの間で細菌や異物が増加すると、生体の防御作用により唾液中の白血球が増加することが知られています。
たんぱく質
口腔内細菌や、歯と歯ぐきの間にあるバイオフィルム(プラーク)の影響により、唾液中のタンパク質が多くなることが知られています。
口腔清潔度に関する項目
アンモニア
口腔内の細菌総数が多いと、唾液中のアンモニアが多くなることが知られており、 口臭等の原因になるといわれています
3共有
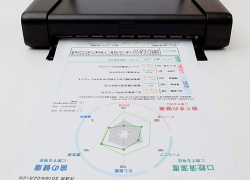 測定結果は5分後にわかりやすいグラフにしてお渡しします。
測定結果は5分後にわかりやすいグラフにしてお渡しします。